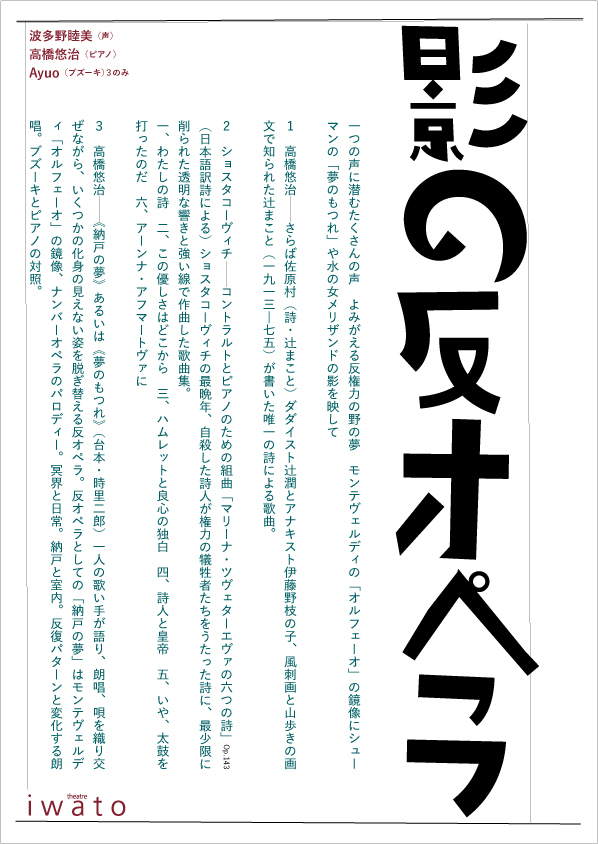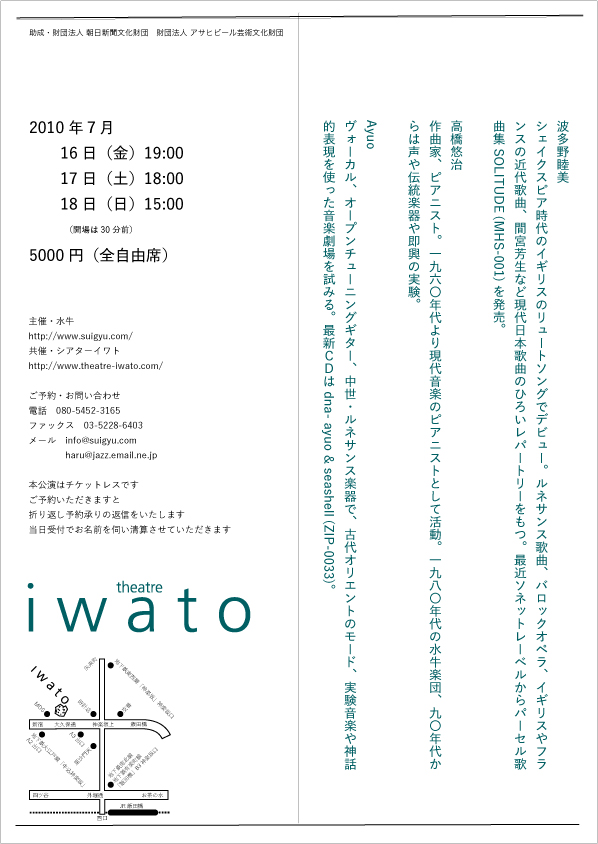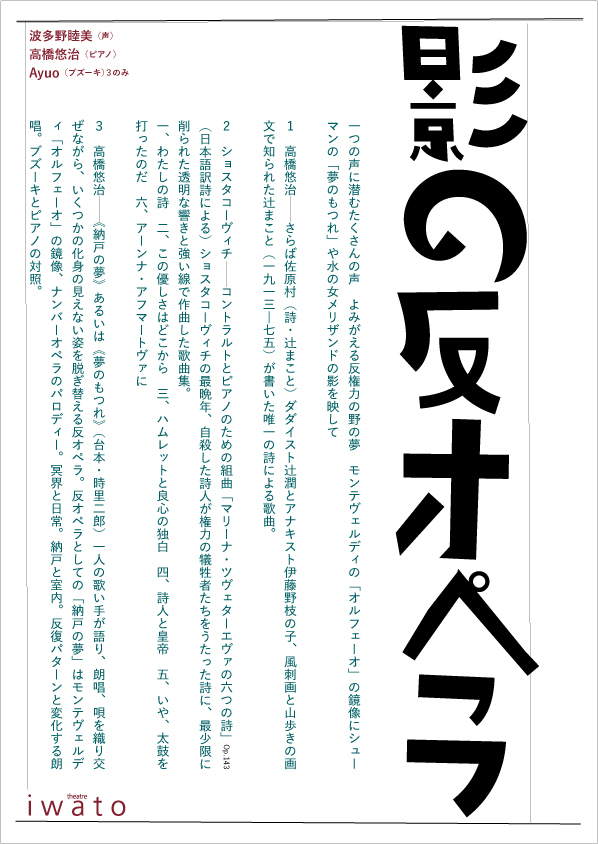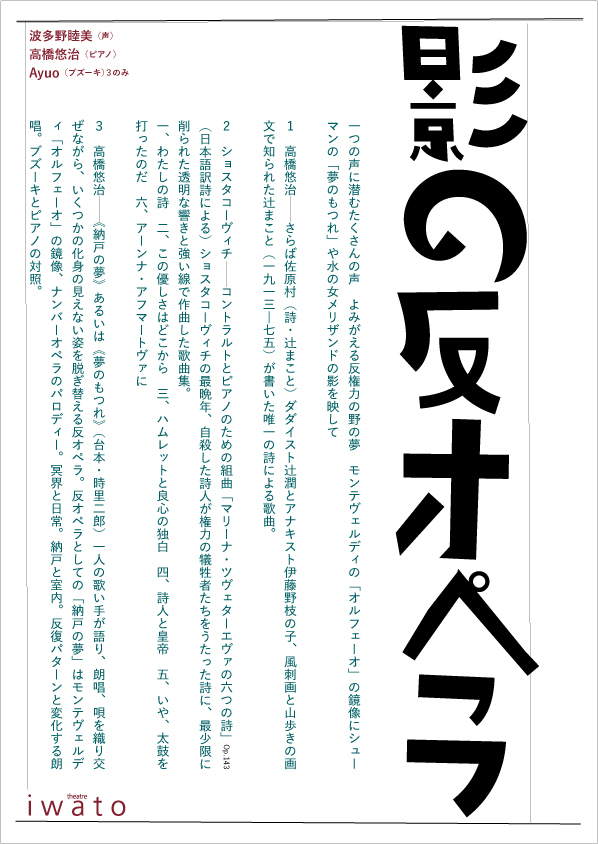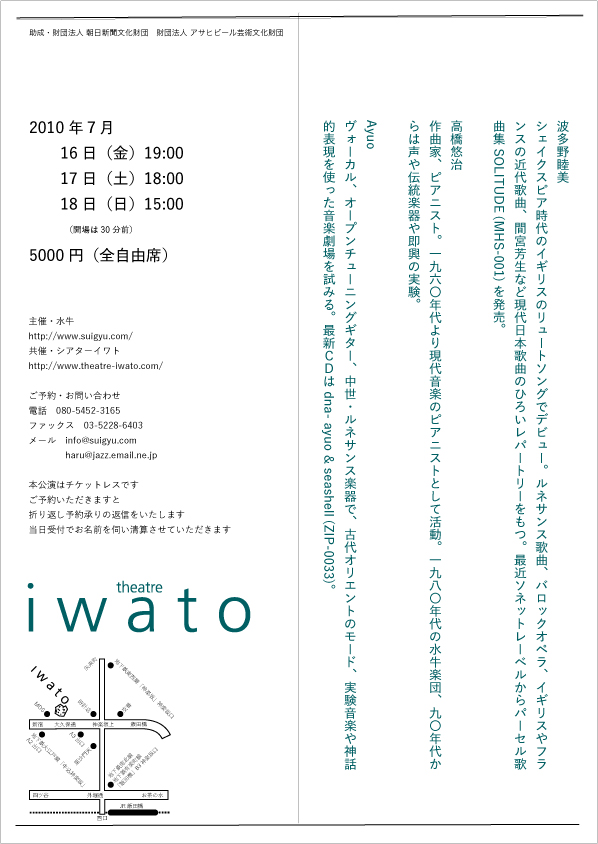影の反オペラ
さらば佐原村 辻まこと
さらば
佐原村(サハラソン)
さらば
おまえの 月夜は もう見られない
馬追いの少年
阿珍(アチン)
おまえのアシ笛に よび戻される
千万先祖の声も
もう聞けない
長根の笹原を 過ぎて行く 風の声は
渡らいながら 旅を続ける
あの人たちの はなしだと
おまえは わたしに教えてくれた
すべての笛は 風の声
阿珍の笛は
いつも わたしの のどもとを あつくした
それから
神楽堰の渡し場
そのしもてで 川海老を釣ることも
もうできない
渡し小屋の いろりで その海老を塩焼にして
渡し守の駄団次と
どぶろくを 飲むことも なくなった
あじさい色の 夕暮れが
足もとから わたしを包むころ
くりやから ひそかに(あんちゃ)と
和尚に声を かける
妹
ただそれだけで
お風呂が わいたのがわかる
声は皆な
いのち
音は皆な
深く
光は 遠く
時は 静かに
ていねいだった
佐原村
さらば
わたしの 佐原村
もう おまえの処へは もどらない
ある日
長根の笹原を 渡ろう
風の中から
阿珍のアシ笛が
わたしの声を
みつける日まで
(1972年7月30日 午後6時30分 武蔵野日赤病院にて)
ショスタコーヴィ
チ:
コントラルトとピアノのための組曲「マリーナ・ツヴェターエヴァの六つの詩」 Op. 143
1.わたしの詩
じぶんが詩人とは知らずに書いた
昔のわたしの詩に
ほとばしる噴水のしぶきのように
花火の火花のように
夢と香の聖堂に
忍びこんだいたずら者のように
わたしの詩は青春と死をうたった
…読まれなかった詩に!…
どの店でもたなざらしになった
(だれも手にとらずにすぎた)
わたしの詩に 貴重なワインのように
その時が来るだろう!
2.この優しさはどこから?
この優しさはどこから?
初めてじゃない 巻き毛の髪を撫でるは
唇も知っている… もっと黒いのを
現れ消えた星も
(この優しさはどこから?)
現れ消えた瞳も
この眼のすぐそばだった
いままでこんな歌を
暗い夜に聞いたことはなかった
(この優しさはどこから?)
歌い手の胸に抱かれて
この優しさはどこから?
どうすればいいの この子
おとなびた旅の歌い手よ
まだ長くもない睫毛して…?
3.ハムレットと良心の独白
「水底(みなそこ) 泥と藻のなか…
彼女は眠る…
…夢も見ずに!」
「愛していた。
だれもできないほどに、
あのひとを!」
「ハムレット!
水底の泥、泥だ!
花の冠は岸の丸太の上だ」
「愛していた、だれよりも…」
「それが愛と言えるのか…
泥にまみれ」
「それでも… 愛…」
4.詩人と皇帝
あの世の
皇帝の列…
「まっすぐに立つ
大理石像
りっぱな金の
スカーフ着けて。」
「プーシキンを誹った
けちな憲兵。
作者を非難し、
著作を削り、
ポーランドを蹂躙した
残酷な暴君。
しっかり心に刻み込め!
詩人殺し 皇帝ニコライ一世。」
5.いや、太鼓を打ったのだ
いや、太鼓の音 おびえた連隊の前
埋葬の時に
皇帝の歯が打ち鳴らした
詩人への敬意のすり打ち。
したしい友だちはだれも
いない、頭に、足に、
右に、左に… 直立不動の
憲兵の胸とつらばかり。
ふしぎなこと… 静かな特等席に
監視付きのいたずらものが?
何か、何か、何かに似てる
誉めて、誉めて、誉め殺す!
ごらん、国が、じっさいは噂とはちがい、
詩人を君主のようにもてなすのを!
だいじに だいじに だいじに,一番
だいじに、だいじに、もうけっこう!
何のつもりか、泥棒が撃たれた仲間を運ぶようにして?
反逆者か? ちがう。 裏口からそっと
出てゆく ロシア一の賢者が。
6.アンナ・アフマートヴァに
嘆きのミューズよ、限りなく美しい!
白夜の狂気の落とし子のあなた!
黒い吹雪をルーシに呼び、
泣き叫ぶ声は矢のように突き刺さる。
わたしたちは打ち倒され 声もなく ああ!
あなたの前に跪く、アンナ
アフマートヴァ! …その名前は…巨大なため息、
それは落ちてゆく、名も知れぬ深みに。
あなたと同じ冠を戴いて
同じ大地を歩む、おなじ空のもと…そして、
あなたの死すべき定めに傷ついた
者は不滅の徴をもって死んでゆく。
歌の街にキューポラは燃え上がり、
メシアの光を彷徨う盲人が称える…
鐘の鳴る街をあなたに贈ろう、
アフマートヴァ! わたしの心とともに…
《納戸の夢》あるいは《夢のもつれ》 時里二郎
○プロローグ
ここは納戸
家の奥の闇の潤い
もう使われることのない調度や
袖を通すことのない着物についた小さな魂の遊ぶところ
窓もなく閉じられた部屋なのに
古い夢
途切れた夢が
行き来する
納戸の奧に
数知れぬ抽斗のついた薬箪笥が
息をひそめた生き物のように据えられている
その抽斗のいくつかは
引き出す時に
かなしいオルガンの音がする
その黄昏のオルガンの音(ね)に誘われて
忘れられた人形や
吹き硝子の壜が流れ寄る夢の岸辺
ここは なんど
ここは なんど
1
わたしが生まれたのは
人の夢の中
ほろびを生きるわたしには
身体がない
人の夢に忍び込んでは
そこをすみかに生きてきた
あなたの夢に迷い込んだのは
そこで見つけた海の色の硝子壜のせい
物語の予感にしずんだ青い色に魅かれて
気がつくとわたしは硝子の壜になっていた
あなたの夢をすみかに生きるために
わたしは壜を脱いで
猫になった
海の色をした瞳の猫に
あなたの夢が望んだとおりに
あなたの夢は入れ子の夢
夢から覚めてもまだそれは夢の続き
納戸のほの暗い中
わたしは 薬箪笥の上にのっていた
○ 朝子の日記 その1(朗読)
やっと薬箪笥がわたしの実家から届いた。
ながらくこの病を飼い慣らしてきたという感慨とひき替えに、いずれ迫ってくる死期を意識するようになった。そんな時、なぜかこの薬箪笥のことがしきりに
思い出された。実家の納戸のほのぐらい場所。思えば、わたしが息子の游(ゆう)くらいの年、いつもそこがわたしの遊び場だった。
用済みになった、たくさんの抽斗で仕切られた薬箪笥に、いつもわたしは大切なものをしまっておいた。ところが、しばらくすると、どこに何を入れたか忘れ
てしまう。それでも抽斗には目印を付けないで、目当てのものとは違うものが入っていたりすると、それを抽斗の魔法のせいにした。空っぽのときは、抽斗が、
どこかよその世界につながっていて、あれはそちらに行ってしまったのだと合点していた。
まだ幼い游を置いて、この世から身を隠さなければならないのなら、せめてあの抽斗の奧とつながっている世界に行きたいと願った。そこなら、幼い游にもい
ずれ見つけてもらえそうな気がして。
2
わたしは猫になって
しばらく納戸で暮らした
だれも入ってこない
広い納戸に
茣蓙が敷かれ
隅に被(おお)いのかかった鏡台がある
あなたは、いつも朝早くに
納戸の戸を開けに来て
夕べにそれを閉めに来た
けれどそこにあなたが入ってくることはない
静かに納戸の戸を開けて
しばらく 奧の薬箪笥を見つめると
裏庭に面した離れに帰る
そればかりか
納戸に寝そべるわたしには
まるで気づかないふうで
わたしが透けて見えるのかしらと
いぶかしく思ったものだ
○ 朝子の日記 その2(朗読)
わたしは明るい陽のさす離れの病室から、今の家の納戸の間に移してもらった。病状がもはや回復の見込みはないことに加えて、それを機に、息子に病がう
つってはならないから、わたしを隔離したほうがよいと強く説いたのだった。その際に、今生のわがままと、懐かしい思い出の薬箪笥を、ここに運んでもらえま
いかと頼んだ。
箪笥が納戸に運び込まれてから、わたしは少女の頃に戻っていたのだろう。
抽斗のいくつかは、引き出すときにオルガンのような音をたてた。どの抽斗が音を出すかわからない。ここかな、それともこっちかなとあてずっぽうに引き出
してみる。そんなたわいもないことをしているうちに、ふといいことを思いついた。
この抽斗の一つ一つに、毎日一つの思い出を入れておこう。思い出を入れる抽斗がなくなるのと、わたしの命が尽きるのとどちらが先か。
3
ある日
ついてこいとも言われないのに
箪笥の上からぽとりと下りて
納戸を出て あなたの後についていく
裏庭までやってくると
千草の乱れる庭のたたずまい
朱や黄や青の絵の具でぽつぽつと付けたような花々が
草の緑にまじる
納戸から抜けてきたわたしには
なだれるようなまばゆい光の粒が息苦しいほど
はじめてあなたに声をかけられたのは
そんな時だった
4
「おいで」
「さあ おいで」
「さあ こっちへおいで」
「みかけない顔だね
どこからやってきたの?
おや 確か どこかで見たような その瞳の色」
そうやってわたしに見入るので
ついわたしも あなたの目を
無防備にのぞき込んでしまう
それでもわたしは
身体を預けることをこばんで
あなたの手をするりと抜ける
けれど
あなたが知らん顔をきめている時には
つい甘えたような声を出して
あなたに忍び寄る
やがて見えない糸にむすばれて
身を隠すことがつらくなる
あなたが見えなくなると
わたしはしきりに切なく鳴いた
すると あなたは
「あさ あさ」とわたしを呼んだ
なにか恥じらうように ためらうように
口ごもりながら 小さくわたしを呼んだ
けれども やがてその名にわたしがなじむころには
「あさ あさ あさ あさ」と歌うように
わたしを呼んだ
○ 朝子の日記 その3(朗読)
薬箪笥が届いた時に、抽斗の一つから、新聞紙で繭のようにくるまれた青い吹き硝子の壜が出てきた。わたしはその壜を手にして、懐かしさでいっぱいになっ
た。
その頃、わたしには大切にしていたお気に入りの人形があった。人形と言っても、目鼻もなく、衣服も身につけていないので、男だか女だかもわからない、か
たい木でできた人形。頭や手足が動くようになっていて、動かすと、きしきしと音がする。時にはぎいぎいと、人形が話しているように聞こえるので、こちらが
話しかけてやると、返事をしたがって、わたしに自分の頭や手足を動かしてくれるように催促するのだった。今思えば、それは家のお祭りの時に使われる厄払い
の形代(かたしろ)だった。
ある日、大切に抽斗のひとつに仕舞っておいたその人形がなくなっていた。そのかわりに、この青い吹き硝子の壜がでてきたのだ。
5
「どうしてこんなに広い屋敷にひとりで住んでいるの」
「これはぼくの夢の中。
夢の外では もう屋敷はくさはらになっている
ひとりでここにいるのは
この屋敷を守るため。」
「こんどはぼくが尋ねる番だ どうしてぼくの夢の中にきみがいるの?」
「ここはわたしの住処 それは きっとあなたが決めたことよ」
「そんな覚えはないけれど。 それにしても きみの瞳の色は 確かにどこかで見たような気がするんだが・・・」
あなたの目の中にわたしが映っている。
猫の「あさ」が映っている
○ 朝子の日記 4(朗読)
わたしの病をうつしてはならないと、納戸に入ってからは、息子の游の顔を見ることはほとんどなかった。
ところがその日、目が覚めると游がいた。游の他には人がついていないから、こっそり入ってきたのだろう。「ゆう、いけませんよ。」とはいったものの、
やっぱり少しでも長く游の顔をみていたかった。
それから游が薬箪笥のそばに行って、抽斗を開けようとするので、思わず「待って」とわたしは制した。
「今はまだ何も入ってないのよ。おかあさんがいなくなったら、この抽斗のどれかに隠れているからね。」すると、隠れん坊をすると思ったのか、ゆうが目を
つぶったので、「おかあさんはまだ隠れないのよ」と言って、青い色の壜を持たせた。「これはこの抽斗の中から出てきたのよ。おかあさんがまだ小さいとき
に、この壜とかくれんぼしていたの。」
それから、游と二人鏡台の前に並んで座った。
だまってじっと鏡の中の游を見た。游も鏡の中のわたしを見ていた。
6
離れであなたにやさしく愛撫されるようになっても
わたしは猫のまま
その不満をあなたに投げると
途方にくれたように
庭の千草に目をさまよわせるばかり
その日はもうこらえられなくて、あなたに質した。
「『あさ』という名前をどうしてわたしに付けたの?
「きっとそうよ。あの納戸には おかあさまのものばかり。着物も箪笥も行李も鏡台もみんなそう。初めてわたしを見たとき、あなたはまるで何もみなかったよ
うにふるまった。そのときわたしは、あなたの強い視線をいたいほど受け止めていたのよ。それははっきり言える。わたしの目の色。そう、あなたはいつも ど
こかで見たことがある目の色だととぼけていたけれど ほんとうは もうあの時に気づいていたはずよ。それが、青い吹き硝子の壜の色であることに」
そう言うと、わたしの身体が、わたしの意志を離れて猫を脱ぎ、吹き硝子の青い壜にかわっていく。
「この壜も おかあさまの形見ではないの?」
「違う。ぼくは壜を愛してるんじゃない。あさを愛している。」
「猫のあさを?」
「違う。ぼくは猫を愛しているんじゃない。あさを愛している。」
「あさは猫よ。」
「いや、違う。あさは人、わたしの恋する人」
青い吹き硝子の壜のわたしは、ゆるゆるとあなたのてのひらの上でふたたび猫にかわっている。
7
さあ、もう一度 今のことばを継いで
あさと呼んで。
わたしを納戸で見つけたときから
おかあさまの身代わりであることがうすうすわかっていたわ
さあ あさ と呼んで。
あなたがわたしをおかあさまと違うと言うのなら
さあ あさ と呼んで
そうすればわかる
わたしが猫のままなら
あなたの恋人にはなれない
さあ あさと呼んで
わたしはどんな顔? あなたのかわいがっている猫の顔?
わたしはどんな顔? あなたが幼い頃に見つめたおかあさまの顔?
わたしはどんな顔? あなたをまっすぐに愛している女の顔?
さあ、あさと呼んで
そうでなければ わたしは猫のまま
あなたの夢に飼われた猫のまま
あなたを強く抱きしめる腕がほしい
あなたのキスを返す唇がほしい
あなたを迎えるからだがほしい
8
わたしたちは夢のもつれを生きていた
あの日から わたしたちは納戸に閉じこもったきり
愛し合うことしかしなかった
わたしが猫を脱いで
あなたの恋人になったしるしを
おかあさまの身代わりでないというしるしを
あなたの身体に見つけたかった
あなたにしても それは同じ
わたしを抱きながら あさと呼ぶとき
おかあさまという毒で口を濡らしはしなかったかと
わたしたちは
お互いの疑いを拭うために
愛し合っていたのかも知れない
わたしたちは夢のもつれを生きていた
からだを合わせるたびに
あなたの夢がほころんでいくのがわかった
強くて若やいだあなたの身体が
木の軋むような音を立て始めた
きいきいきいきいと
わたしが
その音をなぞると
あなたの身体は
いっそうはげしく
ぎいぎいぎいと
あえぐように鳴った
ああ それがわたしたちの夢の軋む音
その音があなには聞こえない
わたしの目には
あなたが 木の人形に見えていることを
あなたは知らない
9
その日 愛し合うのに疲れたわたしたちは
納戸の戸を開けて 裏庭の光の尾を引き込んだ
ふとその光と風にさそわれて 鏡台の被いがゆれ
どちらともなく それに目を向けた
わたしは人になってから自分の顔をみたことがない
あなたはわたしをどんな顔に仕立てたのだろう
あなたが時に 木の人形にみえてしまうのは目のまよいだろうか
そんなことを思いながら
鏡の前にあなたを連れて行き
わたしは被いの布を払った
鏡のなかに わたしはいなかった
あなたがひとりぽつんと立っていた
いやそれは今のあなたではない
まだ幼いころのあなた
その後ろで
幾つあるとも知れない抽斗のすべてが
引き出されたまま
薬箪笥が 口を開けて事切れた生きもののように
無惨なすがたをさらしていた